防災の日(9月1日)自治体・企業に求められる備蓄と災害対策
 |
毎年9月1日は「防災の日」。
1923年の関東大震災の発生日にちなみ制定され、自然災害への備えを見直す機会として広く知られています。
特に地震・台風・豪雨などの災害リスクが高まる中、自治体の防災担当者や企業のBCP(事業継続計画)担当者にとって、防災の日は“備えを実行に移す絶好のタイミング”といえるでしょう。
本記事では、2025年の防災の日に向けて、最新の備蓄用品や空気式防災アイテムの活用例を交えながら、災害への具体的な備え方をご紹介します。
目次
防災の日とは?2025年の注目ポイント
防災の日の目的と由来
「防災の日」は、国民が災害についての認識を深め、被害を最小限にとどめるための備えを促進する日です。
制定の背景には、1923年の関東大震災で10万人を超える死者・行方不明者を出した深刻な教訓があります。
2025年現在では、地震のみならず、異常気象による豪雨や土砂災害などへの備えも重要視されており、行政・企業・地域が連携して災害対策を強化する流れが進んでいます。
自治体・企業に求められる防災対策とは?
備蓄の基本|必要な量とアイテムの選定
災害時のライフライン途絶に備え、3日分の備蓄は最低限必要とされています。
自治体では避難所の運営を見据えた水・食料・衛生用品の備蓄が不可欠です。
企業においても、出勤者の帰宅困難時を想定した防災対策が求められています。
特に注目されているのが以下のようなアイテムです。
・生活用水の確保
折りたたんで保管できる備蓄用の生活用水タンクは、災害発生時にすぐ展開して活用できるため、多くの自治体で導入が進んでいます。
長期保存や持ち運びがしやすいのもポイントです。
・簡易テント、避難スペースの確保
避難所やオフィス内でのプライバシー確保に有効なのが、備蓄向けの簡易テントです。
避難所生活での精神的なストレスを軽減するためにも、有効な備蓄品の一つです。
・仮眠、待機用マットの導入
災害時の備蓄マットは空気で膨らませるタイプで、段ボールベッドに比べて圧倒的に収納スペースを取らず、迅速に設営できるのが特長です。
限られた保管スペースでも導入しやすく、企業や自治体の備蓄に適しています。
実際の導入事例|空気式製品の活用が進む理由
自治体の備蓄事例:省スペースで展開できるタンク
多くの自治体で導入が進んでいるのが、折りたたみ式の備蓄タンクです。
軽量かつコンパクトに収納可能で、水道が断たれた際の生活用水確保に役立ちます。
弊社の貯水タンクは、横浜消防局様への納品実績もあります。
地域の皆様に対して災害時の安心感を高めるツールとしても評価されています。
 |
 |
| 【導入事例】横浜消防納品 | 【導入事例】国交省と消防本部の合同訓練 |
企業の備蓄例:BCP対策としての空気式テント&マット
オフィスや工場においては、保管スペースの問題で備蓄の導入が遅れがちですが、空気式の備蓄テントや災害マットはその課題を解決します。
・設営が簡単:送風機や手動式の空気入れで約5分以内に設置可能
・運搬が容易:軽量で、女性や高齢者でも取り扱い可能
・景品やPR用途にも対応:企業イベントや展示会での訴求にも活用されています
 |
 |
| ポータブルテント | ジョイントエアーパネル |
防災の日を活用した啓発活動と備蓄の棚卸し
自治体の取り組み:地域参加型の防災イベント
9月1日前後に開催される地域防災訓練は、空気式アイテムの展示や体験ブースの導入によって、参加率を高める工夫が見られます。
子ども向けの体験コーナーや、仮設トイレ・テントの設置実演など、実際の災害時を想定したイベントは住民の防災意識を高める効果があります。
企業の取り組み:備蓄の見直しとBCP再点検
防災の日をきっかけに、企業では以下のような活動が推奨されます:
・社内防災訓練の実施
・備蓄品の賞味期限・使用期限の確認
・災害発生時の連絡体制・対応マニュアルの見直し
定期的な「備蓄棚卸し」は、従業員の安全確保はもちろん、企業の信頼維持にもつながります。
まとめ|2025年の防災の日に備えて今できること
「備えあれば憂いなし」。防災の日は、普段の業務の中では後回しになりがちな備蓄や災害対策を“見える化”する絶好の機会です。
特に、空気式の備蓄用品は収納性・展開性の両面でメリットがあり、限られたスペースでも導入しやすいため、自治体・企業問わず幅広く注目されています。
2025年の防災の日を機に、ぜひ一度、自社・自地域の備えを点検してみてはいかがでしょうか。
関連商品
-

-
消防用貯水タンク
横浜市消防局様に97基導入した貯水タンクです。災害時の生活用水の供給や森林火災時の中継槽として活用いただけます。
-

-
災害用水タンク、大型貯水タンクのレンタル・販売
簡単設置で水を貯められる簡易式貯水タンクです。家庭用・消防用・業務用・災害時の避難所での防災備蓄品に活用できます。
-

-
ポータブルテント(日常使いから災害時まで活躍)
日常でも防災でも使える「フェーズフリー」なポータブルテントです。電源不要で5分で設営可能。キャンプ・イベント・避難所などあらゆるシーンに活躍します。
-

-
ウォーターフェンス L1(浸水被害・ゲリラ豪雨対策に)
たった3分で設置できるウォーターフェンスです。高さ0.9mの確かな止水力で、倉庫・店舗・住宅を浸水から守ります。
-

-
ウォーターフェンス M1(浸水被害・ゲリラ豪雨対策に)
軽量で扱いやすく、住宅やオフィス・店舗の玄関口など小規模の開口部に最適。約1分で誰でもすぐに設置できるウォーターフェンスです。
-

-
ウォーターフェンス M2(浸水被害・ゲリラ豪雨対策に)
高い安定性と耐久性を兼ね備えた中型モデル。倉庫前や地下入口など、浸水リスクの高い場所に置くだけで止水効果を発揮します。
関連コラム記事
-

-
【防災用貯水タンクガイド】断水と水害に備える実践対策
災害時の「貯水タンク」は飲料水確保だけではありません。断水30日を想定した組み立て式水槽、給水所で使えるウォーターバッグ、さらに水害時のトイレ逆流を防ぐ水嚢まで。課題別に最適な対策をわかりやすく解説します。 -

-
防災用ウォータータンクの選び方|個人・企業別に比較解説
防災用ウォータータンクは種類が多く、「折りたたみ」「ハード」「雨水タンク」「組み立て式水槽」など用途で最適解が異なります。本記事では個人・企業(BCP)別に、失敗しない選び方とおすすめタイプをわかりやすく解説します。 -

-
給水所の大行列と、企業・避難所の混乱を防ぐ『ウォーターバッグ』の必要性
災害時の給水所には長蛇の列、容器不足、重い水運び…。水を受け取る現実は想像以上に過酷です。個人・企業が今すぐ備えるべき「ウォーターバッグ」の重要性を解説します。 -

-
災害時の生活用水確保|断水でもトイレ・衛生を守る備蓄術
災害時、飲料水と同じように重要なのが「生活用水」。断水でトイレや衛生に困らないために、ウォーターバッグや組み立て式水槽で備える方法を解説します。 -
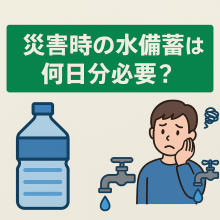
-
災害時の水の備蓄は何日分必要?3日分では足りない理由と実際の復旧期間
災害時の水備蓄は「3日分」では不十分。過去の震災データに基づき、復旧までの期間や家庭・企業で必要な水量、現実的な備蓄方法を解説します。
