災害時の水対策:自治体・企業の備蓄と調達ガイド
災害が起きたとき、私たちがまず直面するのが「水」の問題です。
地震や台風などの大規模災害では、水道管の破損によって断水が発生し、ライフラインの中でも特に水は復旧までに時間がかかる傾向にあります。
水がなければ、飲み水はもちろん、トイレや衛生維持もままならず、住民や従業員の生命と健康に直接的な危機をもたらします。
自治体や企業にとって、水不足は単なる不便さではなく、住民の安全確保や事業継続に関わる最重要課題です。
この記事では、災害時に必要な水の量の考え方から、具体的な備蓄・調達方法まで、防災担当者が知っておくべきポイントを解説します。
目次
災害時に必要な水の量を正確に把握する
まずは、どれだけの水を備蓄すればよいのかを具体的に見ていきましょう。
水は「飲料水」と「生活用水」の2種類に分けて考えることが重要です。
 |
飲料水の必要量:最低3日分、できれば7日分を確保する理由
災害時に必要な飲料水の必要量は、成人1人あたり1日3リットルが目安とされています。
これは、水分補給だけでなく、調理にも使うことを想定した量です。
災害救助法では、発災から最低3日分の備蓄を推奨していますが、近年では7日分の備蓄が望ましいとされています。
その理由は、大規模災害が発生した場合、広範囲での断水や交通網の寸断により、支援物資が届くまでに時間がかかる可能性があるからです。
特に首都直下型地震や南海トラフ地震では、ライフラインの復旧に1週間以上かかることも想定されています。
生活用水の必要量:飲料水とは別に備えるべき水の量
生活用水は、トイレ、手洗い、洗顔、入浴、洗濯など、生活を維持するために不可欠な水です。
飲料水とは別に、1人あたり1日5〜10リットルを目安に備えておきましょう。
生活用水の確保には、災害用貯水タンクや雨水タンクの活用が有効です。
平時からこれらの設備を導入しておけば、断水時でも水を確保でき、衛生環境の悪化を防ぐことができます。
また、火災発生時には消火用水としても利用できるため、多角的な防災対策となります。
 |
商品ページ:組み立て式雨水貯水タンク
自治体・企業が取り組むべき水の備蓄方法と管理
次に、具体的な水の備蓄方法について解説します。
ただ備えるだけでなく、長期的に管理していくための工夫も必要です。
 |
長期保存可能な備蓄水の選定と管理
備蓄水には、5年や10年といった長期保存が可能なペットボトル入りの水を選ぶのが一般的です。
これらは災害に特化して作られており、衛生的で安心して使用できます。
備蓄水の管理には、ローリングストック法が有効です。これは、普段から消費期限が近い水を使い、使った分だけ新しく買い足す方法です。
これにより、常に新鮮な水を備蓄できるだけでなく、備蓄水の入れ替え忘れを防ぐことができます。
災害用貯水タンクの導入と活用
より多くの水を確保したい場合は、貯水タンクの導入を検討しましょう。
仮設貯水タンク、飲料水専用タンク、消防用貯水槽など、用途に応じたさまざまな種類があります。
貯水タンクを設置する際は、安全性を確保できる場所を選び、定期的な清掃と点検で衛生状態を保つことが重要です。
また、タンクの容量は、施設の規模や収容人数に合わせて計算する必要があります。
 |
商品ページ:災害用水タンク
地域のインフラを活用した備蓄
地域の防災力を高めるためには、既存のインフラも有効活用しましょう。
学校のプールや、温浴施設の温泉、あるいは建物の貯湯タンクなども、災害時の生活用水として利用できる可能性があります。
これらの水を利用する際は、ろ過や煮沸といった処理が必要な場合もあるため、事前に利用方法や注意点を定めておくことが重要です。
災害発生後の水の調達と応急給水体制の構築
備蓄だけでは賄いきれない場合を想定し、発災後の水の調達方法も事前に計画しておく必要があります。
 |
迅速な応急給水体制の構築
断水が発生した際は、水道事業体と連携して応急給水拠点を速やかに設置します。
給水拠点までのルートや、給水車の手配を事前に計画しておきましょう。
給水拠点の場所は、住民や従業員が安全にアクセスできる場所に設定し、周知体制を整えることが重要です。
民間企業との連携による水の確保
飲料メーカーやスーパー、物流企業などと災害時協定を締結することも有効な手段です。
協定を結んでおくことで、災害発生時に優先的に水の供給を受けられるようになります。
輸送ルートや供給体制を事前に確認しておくことで、いざという時にスムーズな水の確保が可能になります。
広域的な相互応援体制の構築
近隣の自治体と相互応援協定を結んでおくことも重要です。
自らの地域が被災した場合でも、協定を結んだ自治体から支援を受けることができます。
協定の内容には、水の提供だけでなく、職員の派遣や資機材の提供なども盛り込んでおきましょう。
平時からの計画と訓練が命綱
災害時の水の確保は、発災後に突然できるものではありません。
日頃から、水の備蓄量を計算し、備蓄方法を確立し、調達ルートを確保しておくことが不可欠です。
この機会に、改めて地域や施設の防災計画を見直し、住民や従業員への防災教育を強化しましょう。
定期的に水の入れ替えや給水訓練を実施することで、災害発生時に備えた万全な体制を構築することができます。
平時からの備えこそが、いざという時に住民や従業員の命を守る最大の力となります。
関連商品
-

-
災害用水タンク、大型貯水タンクのレンタル・販売
簡単設置で水を貯められる簡易式貯水タンクです。家庭用・消防用・業務用・災害時の避難所での防災備蓄品に活用できます。
-

-
消防用貯水タンク
横浜市消防局様に97基導入した貯水タンクです。災害時の生活用水の供給や森林火災時の中継槽として活用いただけます。
-

-
エアスリムタンク(Air Slim Pool)
約3分というスピードで簡単設置で水を貯められる丸型プールです。夏場のプール遊びだけでなく、貯水用のプールとしても活用できます。
-

-
小型貯水タンク(50/100/200/350)
災害時の仮設給水タンクとしても活用できる、持ち運びが便利・収納スペースを取らない仮設給水タンクです。
-

-
折りたたみ式大型水嚢(180)
180Lの水を溜めておくことができる大型ウォータータンクです。
-

-
折りたたみ式貯水タンク
1000L貯水可。災害時の生活用水を確保できる簡易型貯水タンクです。
-

-
ウォーターフェンス L1(浸水被害・ゲリラ豪雨対策に)
たった3分で設置できるウォーターフェンスです。高さ0.9mの確かな止水力で、倉庫・店舗・住宅を浸水から守ります。
-

-
ウォーターフェンス M1(浸水被害・ゲリラ豪雨対策に)
軽量で扱いやすく、住宅やオフィス・店舗の玄関口など小規模の開口部に最適。約1分で誰でもすぐに設置できるウォーターフェンスです。
-

-
ウォーターフェンス M2(浸水被害・ゲリラ豪雨対策に)
高い安定性と耐久性を兼ね備えた中型モデル。倉庫前や地下入口など、浸水リスクの高い場所に置くだけで止水効果を発揮します。
関連コラム記事
-

-
【防災用貯水タンクガイド】断水と水害に備える実践対策
災害時の「貯水タンク」は飲料水確保だけではありません。断水30日を想定した組み立て式水槽、給水所で使えるウォーターバッグ、さらに水害時のトイレ逆流を防ぐ水嚢まで。課題別に最適な対策をわかりやすく解説します。 -

-
防災用ウォータータンクの選び方|個人・企業別に比較解説
防災用ウォータータンクは種類が多く、「折りたたみ」「ハード」「雨水タンク」「組み立て式水槽」など用途で最適解が異なります。本記事では個人・企業(BCP)別に、失敗しない選び方とおすすめタイプをわかりやすく解説します。 -

-
給水所の大行列と、企業・避難所の混乱を防ぐ『ウォーターバッグ』の必要性
災害時の給水所には長蛇の列、容器不足、重い水運び…。水を受け取る現実は想像以上に過酷です。個人・企業が今すぐ備えるべき「ウォーターバッグ」の重要性を解説します。 -

-
災害時の生活用水確保|断水でもトイレ・衛生を守る備蓄術
災害時、飲料水と同じように重要なのが「生活用水」。断水でトイレや衛生に困らないために、ウォーターバッグや組み立て式水槽で備える方法を解説します。 -
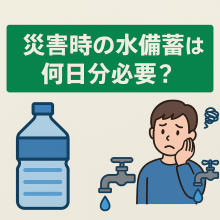
-
災害時の水の備蓄は何日分必要?3日分では足りない理由と実際の復旧期間
災害時の水備蓄は「3日分」では不十分。過去の震災データに基づき、復旧までの期間や家庭・企業で必要な水量、現実的な備蓄方法を解説します。
