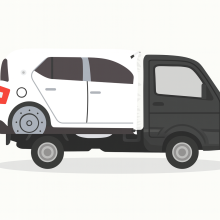可動式車両ダミーとは?安全講習・自動ブレーキ実験での活用と選び方
現代の自動車安全技術の発展や交通安全教育の現場では、「可動式車両ダミー」と呼ばれる機材が活躍しています。
これは実物大の自動車を模したエアー式のダミー車両で、安全講習や自動ブレーキ実験などでリアルな体験を提供するために使用されます。
この記事では、可動式車両ダミーの基本や種類ごとの特徴、主な用途、設置後の取り扱い、そして目的に応じた選び方のポイントについて分かりやすく解説します。
目次
可動式車両ダミーとは?
可動式車両ダミーとは、自動車の衝突試験や安全性能評価に使われるエアー式の模擬車両のことです。
内部に空気を入れて膨らませることで実車大の車体を再現し、対向車や障害物の代替として利用できます。
軽量かつコンパクトに折りたためるため持ち運びが容易で、必要に応じて短時間で設置できるのが特徴です。
実際の車両と比べて扱いやすく、万が一衝突しても本物の車ほどダメージがない安全な教材として注目されています。
送風式と密封式の違い(メリット・デメリット)
可動式車両ダミーには大きく分けて「送風式」と「密封式」の2種類があります。
それぞれ空気の入れ方や運用方法が異なり、メリット・デメリットが存在します。
送風式(エアブロータイプ)
 |
設置時に専用の送風機(ブロワー)を接続し、常に空気を送り込み続けるタイプです。
送風を続けているため多少の穴や傷が生じても形状を維持でき、耐久性の面で優れています。
設営時間が短く、約5分程度で膨らませて使用可能な手軽さもメリットです。
一方で運用中はブロワーの電源が必要で、送風機の作動音が発生します。
また、常時送風のため使用中にダミー本体を自由に移動させることは難しく(動かすと空気が抜けてしまうため)、設置場所を変更する際は一度空気を抜いて再設置する必要があります。
密封式(エアシールタイプ)
 |
内部に空気を密封して膨らませるタイプで、一度規定の空気を入れればその後ブロワーなどの電源は不要です。
電源の確保が難しい屋外やイベント会場でも使いやすく、送風機の音がないため静かな環境での安全講習にも適しています。
空気を入れて栓をするだけなので、膨らませた後はケーブル等に繋がれておらず人力で容易に動かせます。
ただし、密封式は構造上、地面に引きずったり鋭利なもので擦った場合に傷や穴が開くと空気が漏れてしまうため注意が必要です。
送風式のように常時空気を補充できない分、小さな破損でもしぼんでしまう点がデメリットと言えます。
また、製品にもよりますが完全に膨らませるまでにおよそ20分程度かかるものが多く、送風式に比べ設営に時間がかかります。
主な用途
可動式車両ダミーは、安全技術の開発現場から交通安全の教育現場まで幅広く利用されています。
ここでは代表的な用途である安全講習と自動ブレーキ実験での役割について見てみましょう。
安全講習での活用
 |
交通安全教室や企業の安全講習会などでは、可動式車両ダミーが臨場感のある教材として活躍します。
例えば、自動車と人形を使った事故再現では、本物そっくりのダミー車両を対向車に見立てて事故の衝撃を疑似体験させることができます。
実際の事故さながらの状況を安全に再現することで、参加者に事故の恐ろしさや安全運転の大切さを実感してもらう狙いがあります。
シートベルト非着用時の危険性や、適切な車間距離の重要性などを視覚的に伝える場面でも、このダミー車両が用いられます。
軽量で持ち運びも簡単なため、学校やイベント会場へ持ち込んでの出張安全講習にも便利です。
自動ブレーキ実験での役割
 |
自動車メーカーや研究機関では、先進安全技術の開発・検証において可動式車両ダミーが欠かせません。
中でも自動ブレーキ実験(AEBS:自動緊急ブレーキシステムの試験)では、テスト車両の前にダミー車両を配置し、衝突を避けられるかを検証します。
実車とほぼ同じ大きさ・形状のダミーを対向車に見立てることで、センサーやカメラが実際の車両を認識するのに近い条件を作り出し、より正確な性能評価が可能になります。
ダミー同士の衝突であれば車両側もダミー側も大きな損傷を受けないため、繰り返し安全に試験できるメリットがあります。
自動ブレーキ以外にも、自動運転技術や車両の検知システム(レーダーやLiDAR、カメラ認識)の研究において、可動式車両ダミーが実験用のターゲットとして用いられています。
このように、自動ブレーキ実験をはじめとした先進技術のテストには、実環境に近い条件を再現できるダミー車両が重宝されています。
設置後の持ち運びは可能か?
可動式車両ダミーは設置自体が簡単ですが、膨らませた後にそのまま移動できるかはタイプによって異なります。
基本的に、密封式ダミーであれば一度膨らませてしまえば電源やホースに繋がれていない状態となるため、必要に応じて膨らんだままでも移動が可能です。
現場では大人2~3人程度で持ち上げれば、位置をずらしたり向きを変えたりといった移動も容易に行えます。
ただし、地面との摩擦で破損しないよう持ち上げて運ぶ、設置場所を変えたら再度しっかり固定する(強風時に飛ばされないよう重りを載せる・ロープで固定するなど)といった配慮は必要です。
一方、送風式ダミーの場合は使用中常に送風機と接続して空気を送り込んでいるため、膨らんだ状態で頻繁に動かすことには適していません。
無理に移動させると送風機のホースが外れたり電源コードが引っ張られてしまう恐れがあるため、基本的には設置場所を決めたらその場に固定して使用します。
もし別の場所へ動かす必要がある場合は、一度送風を止めて空気を抜き、移動先で改めて設営し直すのが安全です。
送風式は設営・撤収に時間がかからない利点がありますので(数分程度で再膨張可能)、移動のたびに再セットアップする運用でも大きな問題はないでしょう。
いずれのタイプも、現場で扱う際は周囲の安全確認や機材の状態チェックを徹底し、事故防止に努めることが大切です。
選び方のポイント
最後に、用途に合った可動式車両ダミーを選ぶためのポイントをまとめます。
購入やレンタルを検討する際は、次の点に注目して比較するとよいでしょう。
利用目的と環境
まずは主な利用シーンを想定しましょう。
例えば、屋外の交通安全イベントで使用するなら電源不要の密封式が適しています。
一方、実験施設内で頻繁に自動ブレーキ試験を行うなら、短時間で設営でき耐久性も高い送風式が向いています。
安全講習など静かな環境で使う場合は密封式(静音性◎)がベターです。
耐久性・安全性
ダミーが損傷するリスクへの許容度も選定基準になります。
送風式は穴が空いても常時空気を送り続けるため大きくしぼむ心配が少なく、ハードな使用や繰り返しの衝突実験に耐えやすいです。
密封式は鋭利なもので突いた場合などに弱いものの、通常の使用範囲では問題なく繰り返し使えます。
どちらも衝突時の安全性は高く、実車同士の衝突に比べ被害が格段に小さい点は共通しています。
設置のしやすさ
準備や片付けにかかる時間・手間も重要です。
送風式はブロワーをつなげば約5分程度で膨らみ、省力的です。
密封式は空気投入にやや時間がかかりますが、一度膨らませてしまえばその後の取り回しはしやすくなります。
保管時は両タイプとも折りたたんでコンパクトに収納できるため、省スペースで管理可能です。
価格とコスト
製品の価格はサイズやカスタマイズの有無によって様々です。
一般に送風式はブロワー等の機材込み、密封式は高耐久の素材を使う傾向があり、どちらが高価かは一概に言えませんが、用途と予算に見合ったものを選ぶ必要があります。
購入する場合は耐久性の高さから長期的なコストパフォーマンスも考慮しましょう。
利用頻度がそれほど高くない場合や短期間だけ使いたい場合には、レンタルサービスを利用できる製品もあります。
レンタルなら初期費用を抑えつつ必要な期間だけ使えるため、経済的でおすすめです。
関連商品
関連コラム記事
-

-
【限定3台】安全教育を革新する車両ダミー!交通安全教室や講習の教材に
交通安全教室や企業の安全講習に最適な実物大車両ダミーが限定4台で即納可能!自動ブレーキ(AEBS)実験や死角確認など、座学では得られないリアルな体験教育を実現します。軽量で設営も約20分と簡単。耐久性に優れ実車を傷つけない教材の、詳細な料金表とスペック資料を公開中です。 -

-
【限定1台・即納】自動ブレーキ実験の精度を高める「車両ダミー(密封式)」活用ガイド
【限定1台・即納可】自動ブレーキ(AEBS)評価や交通安全教室に最適な「密封式車両ダミー」の在庫がございます。通常納期約60日のところ、今なら待たずに導入可能。電源不要で設営わずか20分、実車へのダメージを最小限に抑えつつ、リアルな衝突試験を安全に実施できます。筑波大学での導入事例も掲載中。 -

-
【製作事例】車両ダミー(密封式)
衝突実験や安全講習に最適な密封式車両ダミーの製作事例をご紹介。お客様のご要望に合わせ、SUV・セダン型のリアルなデザインかつ、シックなグレーのデザインに仕上がりました。 -

-
自律走行車(AV)・ADAS開発に車両ダミーの活用を
自律走行車(AV)やADAS開発に欠かせない車両ダミー。4輪バギーの試験用途としてもお問い合わせが増えており、安全な実証環境に最適です。 -

-
【導入事例】エア式車両ダミーを使った衝突試験とは?自動車メーカー導入事例と効果を解説
エア式車両ダミーを活用した自動車メーカーでの衝突試験事例をご紹介。安全性・再現性・軽量性を両立し、リアルな衝突シナリオを実現します。